[Key's Island]
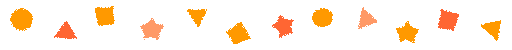
| 読書 |
| << | >> |
050 : 2002-01-18
| タイトル | だから「仕事がうまくいく人」の習慣 |
| 著者 | ケリー・グリソン、楡井浩一[訳] |
| 出版社 | PHP研究所 |
| Comments | 前に読んだ「なぜか「仕事がうまくいく人」の習慣」の続編です。 ローテク手法として、前回の内容がまとめられています。 ハイテク手法として、パソコンやPDAの活用方法が紹介されていますが、内容的には入門レベルでした。 日本に特化した内容の記述が多かったはなぜでしょう?もともと日本向けに書いたのかと思ったくらいです。訳者の方が手を入れているのでしょうか? |
| Key Words |
・専門職のホワイトカラーには整理のしかたや仕事の進めかたを知らない人が多すぎる。 ・「やるべきこと」は記憶せずにメモしておく。 ・もし目的地がなかったら、どこにもたどり着かない。 ・ローテク環境をきちんと整理する。 ・すぐやらなければ生産性が落ちる。 ・最後までやり抜かなければ、すぐやる意味がない。 ・優勝をイメージしないチームは一勝もできない。 ・古きよきビジネスの本質の実現。 |
049 : 2002-01-14
| タイトル | 親子で伸ばす学習戦略 |
| 著者 | 中山 治 |
| 出版社 | 宝島社 |
| Comments | 来年度から、義務教育が週休二日制になりますね。ということもあり、教育関係のものを読んでみました。 著者の場合も、国の進めるゆとり教育は間違っていると考えていらっしゃるみたいです。 学校のタイプ別に参考書や、塾選びについて具体的な説明があります。うちの近くには学習塾なんてないから、塾の話にはついていけないものがありました。 学力養成を本来の目的とするというのは正しいでしょうね。ただ、確かに今の教育システムでは、得点力養成も必要になってしまいすね。 |
| Key Words |
・日本の教育は学力軽視の方向に進んでいる ・思考型の秀才と暗記型の秀才 ・学力養成を主軸とし得点力は方便として利用する ・知識は考える力の前提 ・勉強は最後は自分 ・抽象化の能力を伸ばす ・「脳の酷使」が頭を悪くさせる ・勉強は本来楽しいもの ・幹と枝葉を区別する ・学力と得点力は違う ・個性、創造性は戦いだ |
048 : 2002-01-07
| タイトル | アメリカ人にはできない技術 日本人だからできる技術 |
| 著者 | 中谷彰宏 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| Comments | 有線ブロードネットワークス社長の宇野康秀さん、ACCESS社長の荒川 亨さん、アルファ・オメガソフト社長の佐々木隆仁さんとの対談がそれぞれまとれられています。 前にACCESS社長の荒川さんの講演を聞いたことがあって、面白かったので、この本を読んでみました。 テクノロジー勝負の時代という内容なのでちょっと嬉しいですね。 何度も、「日本ほどインフラの整備された国はない。」と出てきます。「ほんとかな?」って感じですけどどうなんでしょう?光ファイバの普及は意外と早いのでしょうか?? |
| Key Words |
・そろそろテクノロジーの勝負になってきた ・なんでもまず「人ありき」 ・仕事としては採用すれば能力を判断できる ・ヒントは「今までやってきたこと」の中にある ・正当に評価される時代が来た ・日本ほどインフラが整った国はない ・自分をどう利用してもらえるか ・これからの時代は「好き、嫌い」が大事 ・コアのテクノロジーを持つ者が強い ・基本的にニーズから生まれないものはない ・技術者は技術だけのプロでは成功しない ・左脳でモノをつくると差別化できない ・哲学があるかないかが成功の境目 ・哲学がなければ技術は進歩しない |
047 : 2002-01-02
| タイトル | 万有縁力 ネットの向うに人が見える |
| 著者 | EC研究会とってもe本プロジェクト編 |
| 出版社 | プレジデント社 |
| Comments | インターネットでの情報発信で注目されている人たちを取り上げ、取材形式で綴られています。 やっぱり重要なのは人だなと感じました。 私もホームページは「自分自身に情報発信」の方針で地道にやっていきたいと思います。 |
| Key Words |
・ネット時代の縁結びの力 ・たった一人から始まるIT革命 ・子供は社会のもの ・自分自身に情報発信 ・基本方針は正直に伝えること ・何をやり何をやらないかが戦略では重要 ・コンテンツで一番面白いのは人間だ ・優秀なプログラマー:彼らは神様なので人間とは行動原理が違う ・自然は単純で美しい ・仕事は人が生み出し人が成し遂げる |
046 : 2001-12-18
| タイトル | ザ・ゴール |
| 著者 | エリアフ・ゴールドラット:著 三本木 亮:訳 |
| 出版社 | ダイヤモンド社 |
| Comments | 前から読もうと思っていたのですが、ちょっと厚めの本なので、なかなか手にとることができずにいました。 きっかけは「なぜいまさら「ザ・ゴール」が読まれるか」というコラムでした。 ビジネス書でありながら、小説としてもうまく仕上がっていて面白かったです。 本来の目的を考えるというのが重要なんでしょうね。どうも目先だけのことを考えてしまいシステム全体としてどうあるべきかを考えることができないというのが常ですからね。 ついつい部分的な最適化をめざしてしまって、全体として良い方向をめざす全体最適化ってなかなかできないんですよね。 全体として良い方向っていうのは、最終的にはどのように考え、どのように生きるかってことに通じるでしょうけどね。 |
| Key Words |
・TOC(Theory of Constraints:制約の条件の理論) ・生産性とは目標に向かって全社を近づける行為 ・成功したいんだったら自分自身で考えて理解しなくてはならない。 ・依存的事象と統計的変動 ・システム全体を最適化するよう努力しないといけない。 ・ボトルネックのフローを需要に合わせる。 ・自分で試してみないといけない。 ・スループット、在庫、作業経費 ・科学者は仮説を立て、物事の関連性を説く。 ・一番基本的なことからよく考える。 ・真の制約条件はポリシー ・探しているのは思考のプロセス。 ・『ザ・ゴール』のメッセージを社内全体に伝えることが難しい。 ・利潤に基づいた意思決定は行わない。 ・全体最適化の改善手法 |
045 : 2001-12-10
| タイトル | デジタル産業革命 |
| 著者 | 山根一眞 |
| 出版社 | 講談社現代新書 |
| Comments | 全体的に、具体例を挙げてインターネットの歴史がわかりやすく記述されていると感じました。 主役は「個人」というのはいいですね。日本もどんどんそういう方向に進んでいると思います。いい方向です。これまで個人が簡単には入手できなかった様々な情報がオープンになり、また個人の情報発信が低コストで可能となったという観点から、インターネットの普及も大きな影響を与えているのでしょう。 自然環境のよい足助町でSOHO生活をはじめた私としては、これからは「家庭会社」時代だという話にはなんだか嬉しくなってしまいます。実践できる幸運に感謝です。 山根一眞さんは愛知万博の愛知県パビリオン総合プロデューサーを務められるそうですね。 2001年12月11日付の中日新聞30面に「万博は入場者や収支だけではない」と山根さんが講演で協調されたという記事が掲載されていました。講演中でもこの本にかかれている「環業革命」について「日本には『環業革命』を起こす力がある」と語られたようです。 ちょっと愛知万博に興味が湧き始めました。 |
| Key Words |
・経済活動の最小単位は個人である。 ・デジタル産業革命の主役はあらゆる意味で「個人」になる。 ・「家庭会社」時代 ・「環業革命」 ・優れた海外の政治家の導入で日本の建て直しをする |
044 : 2001-12-09
| タイトル | ホームページにオフィスを作る |
| 著者 | 野口悠紀雄 |
| 出版社 | 光文社新書 |
| Comments | 自分でホームページを作りはじめたところに、野口悠紀雄さんから「ホームページにオフィスを作る」なんてタイトルの本が出版されるなんて、大変嬉しいです。 もともと、自分のためにとはじめたホームページです。見てもらうのは友人、知人くらいのつもりでした。この本を読んで、さらに「自分が使うため」という目的意識がはっきりしました。リンクのページなんかは、より自分に役立つものにしていこうと思ってます。 期待される分野として、「SOHO(インターネットを用いる在宅勤務」が挙げられており、ちょっと嬉しくなりました。日本の住環境ではオフィスとして狭すぎる場合が多いので、「共同利用のサテライトオフィス」を整備するとよいと述べられています。こういうのをいつか自分で整備できたらいいなと思いました。 たくさんの人が「SOHOするなら足助町で」なんて考えてくれる環境を整備できたらいいですね。 |
| Key Words |
・ホームページの自作で大きな可能性が開ける。 ・とにかくはじめること。 ・まず、自分だけが使うつもりで作るとよい。 ・更新が重要。 ・共同利用のサテライトオフィス ・ITはコピーのコストを飛躍的に引き下げる。 ・パソコンは修得した上でそれ以外に何をやるかが重要。 ・学校でインターネットを教える必要はない。 |
043 : 2001-11-28
| タイトル | 痛快! 知的生活のすすめ |
| 著者 | 渡辺昇一 和田秀樹 |
| 出版社 | ビジネス社 |
| Comments | どうも、このところ学校教育で進められている「ゆとり教育」って大丈夫かなと考えてしまいます。将来創造的な仕事をするためにも、どうもある程度の詰め込み教育は必要のようだと感じます。日本の教育の進む方向が心配です。 学校教育に関して、クラスの人数が少ないほうが教育効果が高いという内容のアメリカ教育省のレポートが紹介されています。こういう点では、田舎は良い教育環境にあるなと思いました。地元の小学校では1クラス10人前後ですからね。先生のきめ細かい指導が可能ですね。 |
| Key Words |
・子供を伸ばすにはまずプライドを持たせること。 ・内容を減らすとわからない内容が増える。 ・「学歴」ではなく「学力」社会になってきている。 ・アメリカ教育省のレポート。 →「実質生徒数20人以上のクラスを20人未満に縮小すると、平均的な生徒の成績が、50%か60%上がった。」 ・能力主義が世界的な流れになってきている。 ・「無理に勉強させないほうが、独創性が出る」というのは嘘だ。 ・情報と知識はぜんぜん違うもの。 ・子供に親が勉強している姿を見せる。 ・大事なのは出力のトレーニング |
042 : 2001-11-19
| タイトル | 「超」勉強法 実践編 |
| 著者 | 野口悠紀雄 |
| 出版社 | 講談社 |
| Comments | 前に読んだ「「超」勉強法」の続編です。 タイトルの通り、実践的な手法がいくつか紹介されています。 英語の勉強法は実践したい気もしますが、なかなか「毎日2時間2年間リスニング」というのはできそうにないです。 文章記述の勉強法である「毎日150字の日誌を書く」というのは、はじめてみようかなという気になってます。 |
| Key Words |
・目的を明確に持つ。 ・勉強とはすでに存在している知識の体系を習得することである。 ・手抜きの重要性を意識する。 ・手抜きするのは重要な個所に集中するため。 ・実用文は文学と違う。 ・150字文章法。 ・1分間で話せ。 ・最初に全体像を示せ。 |
041 : 2001-11-05
| タイトル | スーパー書斎の遊戯術 |
| 著者 | 山根一眞 |
| 出版社 | 文春文庫 |
| Comments | あいかわらず、山根さんの「スーパー書斎」シリーズは面白いですね。脱線、妄想の嵐です。 今となっては、ちょっと前の調査ということになりますが、「天気欄占有面積では中日新聞夕刊がトップ」だったそうです。朝刊ですが、中日新聞を毎日読んでいるので、なんとなく嬉しくなりました。 |
| Key Words |
・書斎は個人の情報処理工場 ・創造や発想は散歩に生ず。 ・雑誌や新聞は手にした瞬間に処理。 ・腕立て伏せでストレスを解消。 |
| << | >> |
トップ